日本の桜の歴史から見れば、まだまだヒヨッコのソメイヨシノ!
日本にはヤマザクラ、エドヒガン(江戸彼岸)、オシマザクラなど9種を基本に、変種を合わせると100以上のサクラが自生しているそうです。また、これらの自生種をもとに生み出された園芸品種は200以上もあるそうです。
※ 情報源) 公益財団法人 日本さくらの会
当の「ソメイヨシノ」は園芸品種のほうで、幕末に園芸の町として栄えていた旧上駒込村染井(現東京都豊島区駒込)で、オオシマザクラとエドヒガンを交配させて誕生したと言われています。当初、桜の名所である奈良県の吉野山にちなんだ「吉野」の名で登場したものの、山桜が多い吉野の桜との混同を避けるため、明治33(1900)年に地名の「染井」をつけて「ソメイヨシノ」に変更されたそうです。
今では日本の桜の代表的存在であるソメイヨシノ、実は生まれてから百数十年のまだまだヒヨッコなのです。
短命で病気に弱いソメイヨシノ
日本の自生種で一般的な桜の寿命は、「ヤマザクラ:約300年」、「エドヒガン:約500年」と言われていますが、園芸品種であるソメイヨシノの寿命は・・・、なんとたったの「60年」と言われているのです。
このソメイヨシノは、非常に生長が早く、苗木を植えてから10年もすれば立派な成木となり、20年もすれば木の横の広がりが20メートルを超える大木になるそうです。
その反面、早くも樹齢40年ぐらいで木としてのピークを迎え、その後衰えていくそうです。
人間よりも寿命が短いとは驚きました。
また、ソメイヨシノは病気に弱く、折れた枝や枝の切り口から幹を腐らせる菌が侵入しやすく、樹齢50年を超えると幹の内部が腐ってしまうことが多いそうです。
そもそもソメイヨシノが全国に植えられたのは今から70年ほど前で、1945年の太平洋戦争終結を機に“戦後の日本のシンボル”として日本中の焼野原に苗木が植えられたことが始まりだそうです。その後も、日本各地で何かお祝いごとや記念行事があると、度々このソメイヨシノの苗木が植えられました。
ちなみに桜の名所づくりを進めてきた公益財団法人「日本花の会」(東京)は1962年の創設以降、200万本を超すソメイヨシノの苗木を各地に提供してきたそうです。
もうお気づきかと思いますが、日本各地にあるソメイヨシノはその多くが寿命と言われている樹齢60年前後にあるのです。
ソメイヨシノにも個体差があり、100年を超えても未だに毎年満開の花を咲かせているものもあるようですが、多勢は年々幹の内部の腐りと戦っている木のようです。

全然知らなかった・・・
行政主導で進めてほしいソメイヨシノの管理
しかし最近では、枝の剪定方法に加えて殺虫剤の使い方や肥料の与え方、土の入れ替えなども工夫することで寿命は大きく伸ばせるようになったそうです。実際に、青森県弘前市にある弘前城では早くから独自の管理法を確立し、今では樹齢100年を超える古木が300本以上もありいずれも元気に満開の花を咲かせているそうです。
当たり前のように慣れ親しんできた「日本の春の風物詩」を守っていくためにも、日本各地にあるソメイヨシノの古木の管理や世代交代の新しい苗の植え付けを、一日でもはやく各地の行政主導で進めてほしいものですね。
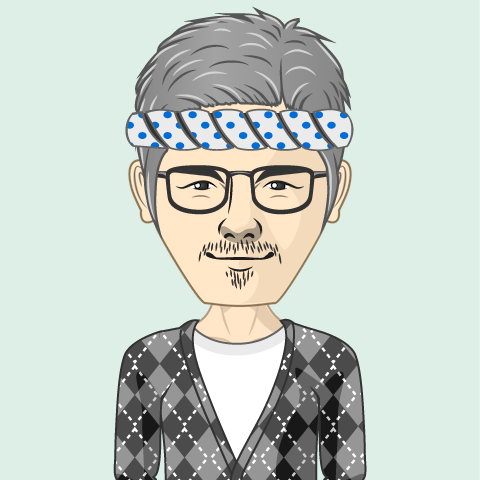
「桜を見る会」ではなく、ソメイヨシノ存続のために税金を使って欲しいものだ!



















