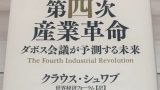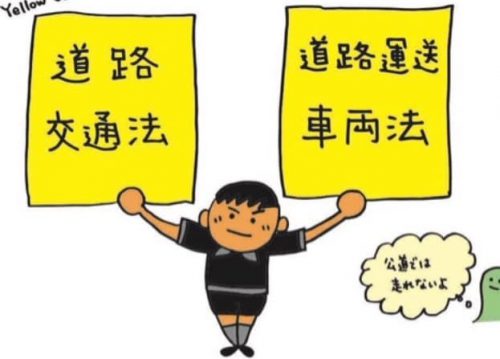3ヶ月ほど前、安倍元首相は政府の未来投資会議で「宅配需要の急増に対し、人手を介さない配送ニーズが高まる中、低速・小型の自動配送ロボットについて、遠隔監視・操作の公道走行実証を年内、可能な限り早期に実行します」と言っていました。しかしながらやっと最近「ヤマト運輸が9月以降、首都圏各地でロボットが公道を走り配送する実証実験を始める」と日経新聞が報じていました。(ただ、9月も中旬になった今現在もヤマト運輸のHPでは報じられておらず真相は不明)
そこで今回は、新型コロナ発生以降、海外では実用化が急速に進んでいるロボットデリバリー(宅配)について色々と調べてみました。
法規制が足かせになり、大幅に遅れる日本
そのような海外に比べ、日本では実用化のメドすら立っていないのが現状です。その一番の理由は、やたら公道上での規制が厳しく、一向に国が規制緩和をしないからだと言われています。今の日本では、どんなに低速でもデリバリーロボットは単独で公道を走行できないよう規制されいるそうです。そのためロボットデリバリーが実現までには、以下のようなプロセスになると思います。
民間企業による今年の秋からの実証実験
↓
来年の春頃の規制緩和法案成立
↓
来年の秋頃に法律施行
という感じなので、都心の一部地域に限ったとしても早くて2021年の後半でしょうね。
早くからロボット先進国と言われ続けてきた日本が、結局実用化は諸外国の1年半遅れですよ。まったく今の日本の政府と役所は、グローバル化時代に不可能なスピード感に欠けると同時に、自分たちの既得権益にばかりしがみついて国民の利益を全く考えていない最低の人達の集まりとしか思えませんね。
日本国内でこれまでに行われた実証実験の内容は?
今回の新型コロナ騒動で、日本でも食事や買物のデリバリーサービスが急速に広がり、ようやく技術音痴の安倍さんも動き出しましたね。そこで、まず初めにこれまでに既に終了したロボットデリバリーの代表的な実証実験をいくつか調べてみました。
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス内実証実験
この実証実験は、2001年創業の自動運転技術開発を手がけるベンチャー企業ZMP社が中心となり、慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスとローソンの協力に得て、2019年1月21日1~31日にキャンパス内で実施されました。https://response.jp/
具体的な実験内容は・・・、
ZMP社が開発した配送ロボットDeliRo(デリロ)を使って、大学敷地内でローソンの商品を無人配送するというもので、世界初の宅配ロボットによるコンビニ無人配送サービスの実証実験となりました。その一連の流れは以下の通りです。
- 実験参加者の大学生は自分のスマホに専用アプリをダウンロードする
- そのアプリからユーザ登録をする
- お昼休み等にアプリからローソンの弁当や飲み物、スイーツなどを注文する
- キャンパス内の仮店舗から指定の配達拠点まで、DeliRoが商品を届ける
- 電子決済後、発注者にはDeliRoのロッカーのカギであるQRコードが届く
- DeliRoが到着したら、発注者はDeliRoのカメラにQRコードをかざすと商品が入ったロッカーが開く
- ロッカーから商品を取出し、ロッカーの扉を閉める
- DeliRoは自動的に店舗に戻る
この実験では商品を注文する際に、受取時刻の指定もできるそうです。
この実験に参加した学生たちからは「食事やドリンク、デザート等の選択肢が増えた」「休憩時間を有効活用できるなどのメリットが生まれた」「便利!かわいい!」といった声が聞かれたそうです。
今回は公道は使わないキャンパス内だけでの実証実験ですが、実は米国ではすでに100校以上の大学がこの実験と同じようにキャンパス内で実用化しているのです。さすが、ベンチャー企業の天国アメリカですね。
<DeliRo(デリロ)の基本スペック>
・ボディサイズは、全長96.2cm、全幅66.4cm、高さ108.9cmと小型で最大積載量 50kg。
・ZMP社が開発した 自動運転ソフト『IZAC』を搭載し、カメラやレーザセンサで周囲を360度認識しながら、最大時速 6km で自動走行。
・笑顔やウインクしたり、声を出して挨拶やお願いをしたりするコミュニケーション機能も備える。
大手町プレイスウエストタワーで行った日本郵便の配送実証実験
この実証実験は、日本郵便が2020年3月3日~4日の2日間、本社ビルの大手町プレイスウエストタワーで行ったものです。
具体的な実験内容は・・・、
イタリアのベンチャー企業が開発したデリバリーーロボットを使い、エレベーターと連動してフロア間を移動し、社内便を配送するものです。その一連の流れは以下の通りです。
- 配送ロボットYAPEは14階にあるメールセンタで社内便を積み込む
- YAPEはエレベーターホールに行き、そこでWiFiを介してエレベーターを呼び出す
- エレベーターを使って社内便の届け先があるフロアに移動する
- 目的フロアに着いたらYAPEはエレベーターを降り、社内便の届け先に一番近いドアに向かう
- ドアそばに着いたら届け先に到着をメール通知する
- 受け取り人に社内便を渡した後、再びセンターへ戻る
このように、配送ロボットYAPEはオートナビによるフロア間のルートの設定やエレベーターにネット経由で呼び出しや扉の開閉、指定階の指令を出すことにより、異なるフロア間の移動をすべて自律走行で可能にしているのです。
実は、この日本郵便の実験より前の2019年12月には竹中工務店と三菱電機が協業し、前述のZMP社のデリバリーーロボットCarriRo Deli(キャリロデリ)を使って竹中工務店の本社でエレベーターと連携させた無人配送サービスの実証実験を実施しているのです。
自分も昔勤めていた会社は、何千人もの社員が一つビル内で働く大企業だったので、社内便配達専門人員が5~6人いたことを覚えています。ようやく、人間もこのような単純労働から解放されるんですね。
広大な公園内で楽天と西友が協同で実施した商用配達サービス実証実験
この実証実験は、楽天と西友が2019年9月21日(土)から10月27日(日)までの約1カ月間の土日に実施したもので、実験とは言え一般消費者に商品を販売しデリバリーー料金を徴収しています。実施した場所は、神奈川県横須賀市の「西友 リヴィンよこすか店」とその隣にある「うみかぜ公園」で、中国のベンチャー企業「京東集団」が開発したデリバリーーロボット「UGV」を使って行なれました。
具体的な実験内容は・・・、
- 公園でバーベキューやピクニックを楽しむ行楽客が、スマホにアプリ「楽天ドローン」をダウンロードする。
- お客はそのアプリから「西友 リヴィンよこすか店」内の生鮮品を含む食材や飲料、救急用品など約400品目から商品を選択注文し、「楽天ペイ」で決済する。
- デリバリーーロボットUGVは、公園入口に設置されたセンターで注文された商品を積み込みむ。
- UGVは公園内に設けられた6か所の配達場所のうち、顧客が指定した所に向かう。
- 配達場所に着いたら、顧客に到着したことをメールで通知する。
- メールを受取った顧客は配達場所に行き、通知された暗証番号を使ってUGVのボックスを開け商品を受け取る。
- デリバリーー後、UGVは自動的にセンターに戻る。
このように行われた実験ですが、公道こそ走りませんでしたが、公園という様々な人が行き交う場所で、更には商品の実販売という非常に実用化時に近いものでした。なお、今回のサービスでは時速5~6km/hで走行でデリバリーー料金は300円でした。
ちなみに、この機種の最高速度は約20km/h、最大積載量は50kgだそうです。
他国に比べ道路の整備状態よく、また高齢化に伴う人手不足が深刻な日本は、世界中の配送ロボット会社が狙っている「おいしい」市場なんだそうです。何とか将来性が見込まれるこの市場では、日本の企業も頑張って欲しいものですね。
海外では既に日常生活に溶け込みつつあるロボットデリバリー
今現在、デリバリーロボットの実用化が最も進んでいるのは米国です。実は、米国では「ロボットの公道自律走行許可」を全国一律ではなく各州政府が勝手に認可出来るのです。そのため先進的な考えを持っている州では、いち早くロボットによるデリバリーを実現しているのです。
では、海外ではどのように実現しているのでしょうか。いくつかの実例を調べてみました。
米国でのレストランデリバリーサービス及び食料品宅配サービス
米国ミシガン州の南部に位置する人口11万人ほどのアナーバー市では、デリバリーロボットを使ったレストランデリバリーサービス及び食料品宅配サービスが、2020年1月から行われています。
この事業を手がけるのは地元ベンチャー企業Refraction AIで、利用しているのは軽量でバイクのような自律型3輪ロボットREV-1です。
具体的なサービス内容は・・・、
利用者が同市のダウンタウンにあるレストランや食料品店に商品を専用サイトからネットで注文すると、半径3マイル(約5km)以内ならデリバリーロボットREV-1が配達してくれるというものです。また、商品が到着したらREV-1を開け商品を取り出すための専用のコードは、到着後に発信される自動到着メールに記載されています。なお、配送料は商品代金の15%でレストランや食料品店が支払います。
この実例の凄いところは、一般車道を25kmというかなりのスピードで走るという点です。さらに下の映像のように雪が残るような悪路でも平気なようです。日本では、考えられないですね。
REV enjoyed the first snow of the season!
📸 https://t.co/RxJHVtTDsV via https://t.co/QP6BycLI6K pic.twitter.com/BmSfqfXlad
— Refraction AI (@RefractionAI) November 11, 2019
<REV‐1の基本スペック>
・ボディサイズは、全長152cm、全幅76cm、高さ130cmで重量約50kgで収納量は450ℓ(約50cm四方)です。
・Refraction AI社が開発した自動運転ソフトを搭載し、カメラやレーザセンサで周囲を360度認識しながら、平均時速25km で自動走行する。
英国ロの街ミルトン・ケインズでの宅配便サービス
英国ロンドンの北西部に位置する人口23万人ほどのミルトン・ケインズでは、世界初のデリバリーロボットを使った宅配便サービスが2018年11月から行われています。
この事業を手がけるのは、米国の配送ロボット開発・サービス提供するベンチャー企業Starship AI社で、利用しているのはデリバリーロボットのメーカー「Starship Technologies」の開発した小型の自立型6輪スターシップロボットです。
具体的なサービスの内容は、月額約10ドルの契約さえすれば、何度でもネットから注文した様々な商品をこのロボットが指定された日時に配達してくれるそうです。ちなみにこの宅配ロボットは、これまで累計2万件の配達を行い、累計走行距離は20万キロに及んでいるそうです。
<スターシップロボットの基本スペック>
・ボディサイズは、全長69cm、全幅56cm、高さ56cmで重量約20kgで最大積載量は10kgです。
・移動速度は6km/h(最高16km/h)で行動範囲は半径3kmです。
・GPS、360°カメラ、超音波レーダーを使って自動走行します。
またこのロボットは小型ですが、6輪を巧みに使い道路の縁石も乗り上げての走行でき、夜間や雨や雪でも、またでこぼこした未舗装路でも動くことができるのが特徴です。
このスターシップロボットのサービスは、2018年ミルトンケインズで始まって以来、着実にサービスを拡大させ、現在では米国のアリゾナ州テンペ、ワシントンD.C.、カリフォルニア州アーバイン、カリフォルニア州マウンテンビュー、テキサス州フリスコなどでもサービスを開始しているそうです。
このようなロボットによる自動配送は、欧米諸国だけではなく中国でも次々と実用化されており、かってはロボット先進国と言われた日本は、悲しいかな大きく遅れをとっているのが現状です。
明日誕生する菅内閣は、平均年齢が59.9歳,、経済産業省大臣の梶山さんは64歳、デジタル省大臣の井上さんは62歳、こんなおじさんばかりで本当に世界の最先端ビジネスについていけるのでしょうか?日本の未来が心配です。
皆さんはどう思いますか?