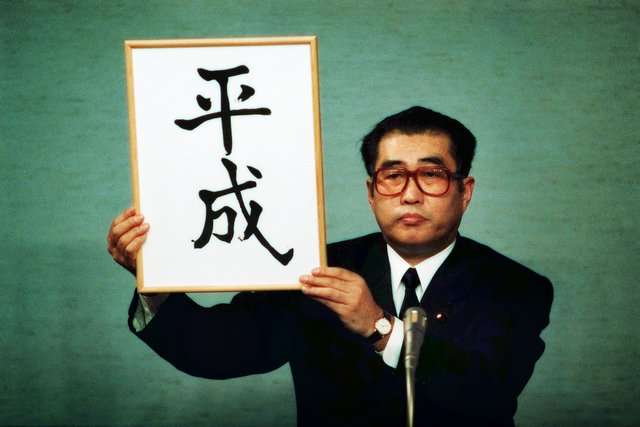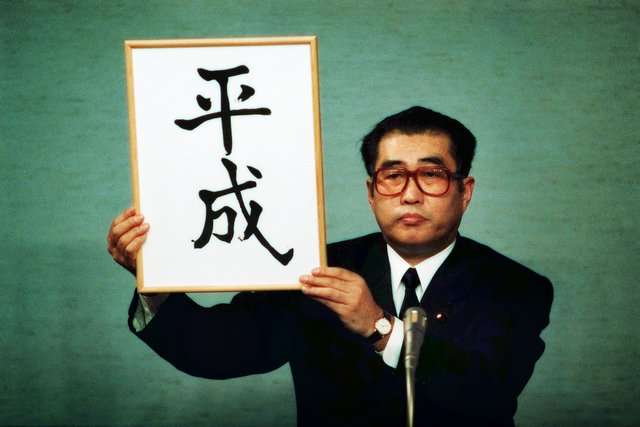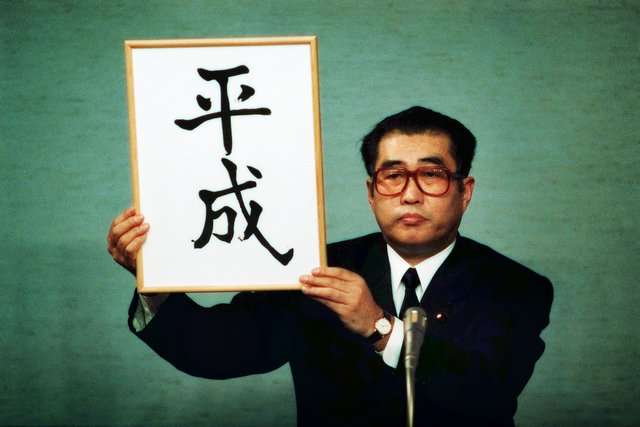グローバル化が進展した現代では、日頃からよく接しているメディアでも「国際収支」とか「貿易収支」「経常収支」という言葉を目にしますね。自分は大学で経済を専攻していたにもかかわらず、恥ずかしながら上記言葉の正確な意味がわからないまま日々のニュースを聞き流してきました。
ところが先日読んだ「101のデータで読む日本の未来」という本の中でも、これらの言葉が多用されていて、今ひとつ本の内容が理解できずモヤモヤしていました。
そこで今回はこれらの言葉について詳しく調べてみました。
「国際収支」という言葉が最上位概念!
いろいろ調べて見ると、これらの国際経済用語はどうやら国際通貨基金(IMF)の「国際収支マニュアル(Balance of Payments Manual)に基づいて定義されているようです。まあ、国ごとに異なる定義がなされていたら「経済のグローバル化」は進められないので、国際機関であるIMFが決めるのは当たり前でしょうね。
ちなみにこのマニュアルは経済の進展多様化に合わせてリバイスされるため、これらの言葉の定義も変化しているようです。現在日本の財務省が使っている定義は2014年に決められたものだそうです。
自分は大学時代に学んだ40年も前の知識で先の本を読んでいたので、理解できなかったのも当然ですね。
財務省の方では2014年に、国際収支関連統計に関する大幅な見直しを実施し、現在に至っているとのことです。
さて話を具体的な定義の内容に戻しますが・・・、
これらの言葉の中で一番上位にあるのは「国際収支(Balance of Payments)」という言葉で、その定義は以下のようになっています。
“国際収支とは、一国が外国との間で行うすべての経済取引の収支のこと。また、この国際収支は経常収支、資本移転等収支、金融収支の3つの項目からなる。”
まあ、わかりやすく言うと「日本に住んでいる個人や日本の政府・地方自治体及び日本にある企業等の法人が海外行った経済取引で生じた金銭的収支の合計」ということです。故に「国際収支が黒字ならその国は富み」、逆に「赤字ならその国は貧しくなる」ということです。
「国際収支」を構成する3つの要素の定義は?
①経常収支
一国が海外と行った貿易や投資といった経済取引の収支の合計。
②資本移転等収支
一国が外国に行った無償援助や債務免除、及び特許権や著作権などの非生産・非金融資産の売買の収支の合計。
③金融収支
一国が海外で行った金融取引の結果生じた有価証券売却益や受取配当・利息などの金融収益から支払利息,有価証券売却損などの金融支出を引いた合計。
②と③かなり難しいのですが、近年日本は②③の黒字が増えているようです。
「経常収支」を構成する4つの要素の定義は?
①貿易収支
国内居住者と外国人(非居住者)との間のモノ(財貨)の取引(輸出入)の収支の合計。
②サービス収支
国際貨物、旅客運賃の旅行者(=非居住者)の宿泊費、飲食費等の受取・支払や
金融商品売買等に係る手数料等の受取・支払や特許権、著作権等の使用料の受取・支払の収支の合計。
③第一次所得収支
一国海外投資から得た利子・配当などの収支の合計。これには本国親会社と海外子会社との間の配当金・利子等の受取・支払も含まれています。
④第二次所得収支
一国の居住者と非居住者との間の対価を伴わない資産の提供に係る収支状況を示す。これには官民の無償資金協力、寄付、贈与の受払等も含まれています。
なんかどんどん難しくなってきてますが、近年日本は②③の黒字が増えているようです。
昔からそうですが、本当に金融関係の用語はわかりにくいですね。