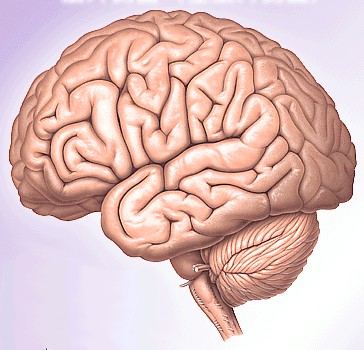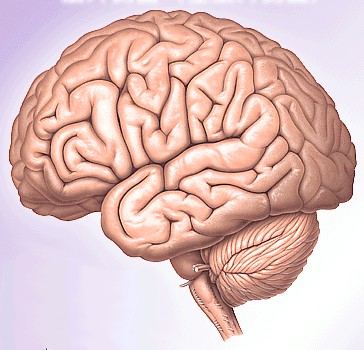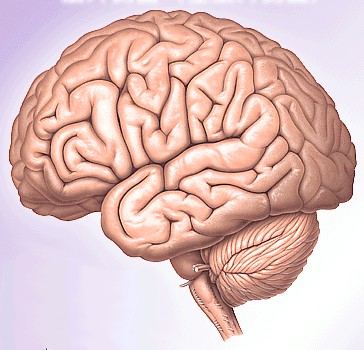自分は3年ほど前から「Whill」という電動車椅子を利用し都心部で細々と生活しているのですが、最近は「国内一人旅」にはまり、先日も愛媛県松山市に行ってきました。
当初自分は「松山は人口50万人程度の地方都市なので、バリアフリー化はあまり進んでなく、宿とその周辺で過ごすしかないだろう」と考えていたのですが、行って見てビックリ!何故か市内公共交通機関のバリアフリー化が非常に進んでいるのです。その為、予想外に様々な観光スポットにも容易かつ安くいくことができたのです。
そこで今回は、日本における鉄道やバスなどの「公共交通機関のバリアフリー化」についていろいろと調べてみました。
日本で公共交通機関のバリアフリー化が進展したのはここ5年ほど!
自分がまだ健常者だった10年前には、確かに電車やバス内で車椅子はおろかベビーカーすらほとんど見かけることはなかったような気がします。ところが最近では、昼間に都心部を散策していると電車やバスの中でも当たり前のようにベビーカーや車椅子を見かけるようになりました。私たち庶民の給料は30年近く全然変わらないのに・・・、都心部のバリアフリー化はたった10年で一気に進展したのです。
なぜ、バリアフリー化は一気に進展した?
自分は10年近く都心部で車椅子生活をしているので、よく分かるのですが、「バリアフリー化急進展」の理由は「2020年東京オリンピック&パラリンピックの開催」です。このオリンピックは初の同一都市同時開催だったので、誘致する際にIOCの方から「東京及び日本全体のバリアフリー化の推進」を求められたのです。まあ「外圧でしか変われない日本」の典型的な例ですね。
ご存知の方は少ないと思いますが、実は今から20年ほど前の2005年9月に日本政府は正式に東京オリンピック&パラリンピックの誘致を開始し、すぐさま翌2006年6月には「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(通称バリアフリー新法)を成立させたのです。いかにも日本らしいですね。
結局、コロナの関係もあり完全に「不発」に終わった東京オリンピック&パラリンピックですが、このバリアフリー新法に基づいた「東京をはじめとする日本のバリアフリー化進展」だけが東京オリンピック&パラリンピックの唯一の成果だと自分は今でも思っています。
参考)バリアフリー新法の概要
バリアフリー新法は、「障害者や高齢者などの身体的な制約を持つ人々が、社会的な活動をしたり円滑に公共施設を利用できるようにする」ための法律で、障害者や高齢者などが社会参加をしやすくすることを通じ、より多くの人々の社会的な活動や公共施設の利用を活性化を目指しています。具体的には以下のようなことが定められています。
1.建築物や公共施設のバリアフリー化
障害者高齢者などが建物や施設を利用しやすくするため、バリアフリーな設計や設備の導入を推し進める。例えば、段差の解消、手すりやエレベーターの設置など・・・。
2.交通網のバリアフリー化
公共交通機関や道路などの交通環境をバリアフリー。バスや駅のバリアフリー化を推し進める。例えば、車いすの利用が可能な車両や施設の整備など・・・。
3.情報のバリアフリー化
障害者が情報を得るためのアクセスを容易にするための取り組みがを推し進める。例えば、公共の掲示物やウェブサイトなどがバリアフリーな形式で提供情報するなど・・・。
松山市の公共交通機関のバリアフリー化が進んでいる理由
実は、東京や大阪という大都市への交通の便が悪かった松山市は、2000年代初頭から高齢者の比率が高く、早くからバリアフリーな環境が求められていたのです。そのため、なんと2003年には「お年寄りや障害者にやさしい日本一のまちづくり」をスローガンに「松山市交通バリアフリー基本構想」を策定し、駅などの旅客施設、周辺の道路、駅前広場、信号機等のバリアフリー化を一体的に進めていたのです。
そのため、2006年にバリアフリー新法が制定された時には既にバリアフリーに対するしっかりとした考え方と計画を持っていたのでいち早く国や地方自治体の補助金制度をフル活用しながら、着々と市内の公共交通機関のバリアフリー化(バス停や駅舎の整備、エレベーターの設置、車両内の段差解消や車椅子対応スペースの確保など)を推進していたのです。
さらに驚いたのは、伊予鉄道の松山駅にはホームに可動型スロープが埋め込まれていて、駅員さんがまるでテレビのリモコンのようなものを押すだけでスロープが自動的に渡されたのです。下のビデオはYouTubeの伊予鉄道公式ホページにある実際の装置の稼働映像です。
自分は「こんなモノ、東京でもまだ無い」とひたすら感動していたのですが、東京に戻って来てからいろいろ詳しく調べてみると・・・なんとこの装置京急の子会社が開発し、2000年2月には京急の羽田空港駅と上大岡駅に設置されていたのです。ただ、残念なことに2000年ごろから首都圏では急速に鉄道各社の相互乗り入れが進んだため、この装置は首都圏ではほとんど普及しなかったようです。理由は、電鉄各社や路線ごとに使用している車輌が違うため、乗車口の場所も微妙に異なり「ホーム埋め込みのスロープでは対処できないからだそうです。そして結局、現在のように駅員さんがいちいち手で設置する原始的な方法が大半となっているそうです。これだけIT技術が進歩した現在、何かいい方法があるように思うのですが・・・。
松山市に比べ、東京都や政府は「やれバリアフリーだ、やれ保育園待機児童ゼロだ、少子化対策だ・・・、温暖化対策だ・・・、軍備増強だ・・・、」などと行き当たりばったりの政策を次々と中途半端に推し進めるのは、その中心だった安倍さんもいなくなったのだから、そろそろやめてほしいですね。いたずらに借金を増すだけでしょう。ほんとこれから先、日本は大丈夫なんでしょうか?